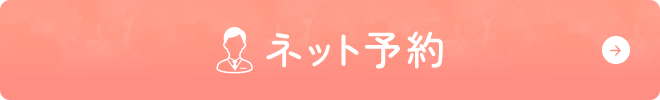睡眠障害とは
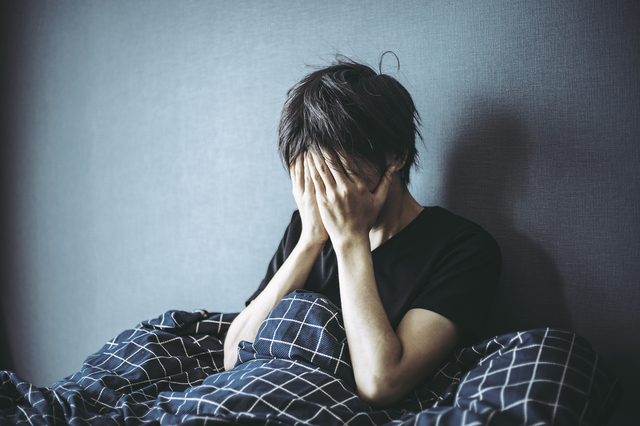 睡眠障害とは、「夜、なかなか眠れない」「途中で何度も目が覚めてしまう」「昼間に異常なほど眠くなる」といった睡眠に関するトラブルが長く続き、日常生活に支障をきたす状態を指します。眠ることで体や心をしっかりと休ませられないと、疲労や集中力低下、気分の不安定さなど、さまざまな不調が現れます。
睡眠障害とは、「夜、なかなか眠れない」「途中で何度も目が覚めてしまう」「昼間に異常なほど眠くなる」といった睡眠に関するトラブルが長く続き、日常生活に支障をきたす状態を指します。眠ることで体や心をしっかりと休ませられないと、疲労や集中力低下、気分の不安定さなど、さまざまな不調が現れます。
当院では、土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、日常生活に支障をきたすまえに、お気軽にご相談ください。
単なる睡眠不足と思っていませんか?
私たちの体は、睡眠を通じて疲労を回復するだけでなく、ホルモン分泌や脳の情報整理、免疫機能の調整など、健康維持に欠かせない多くの働きを行っています。特に、深い眠り(ノンレム睡眠)は、肉体の修復や成長ホルモンの分泌に関わり、レム睡眠は記憶の整理や感情の安定に影響を与えます。そのため、睡眠の質が悪いと、単に「眠い」だけではなく、体のあちこちに不調が出るのです。
眠れない状況を放置すると、症状が慢性化し、心身に深刻な影響を及ぼすこともあるため、早めの対応が重要です。
睡眠障害の種類と具体的な特徴
1.不眠症(インソムニア)
 不眠症は、最も多い睡眠障害の一つです。
不眠症は、最も多い睡眠障害の一つです。
- 寝つきが悪い(入眠困難)
- 夜中に目が覚める(中途覚醒)
- 朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)
- 眠りが浅い(熟眠障害)
といった症状があります。
病気の発症は精神的ストレス、仕事上のプレッシャー、家庭の問題などの心理的要因が多いですが、他にも環境要因(騒音、部屋の温度)、身体的要因(痛みやかゆみ)、薬の副作用も関係します。例えば、就職したばかりの若い会社員が業務のプレッシャーから寝つけなくなり、次第に「今夜も眠れないかもしれない」という不安が原因でさらに悪化してしまうケースがあります。
放置すると慢性的な疲労、集中力の低下、気分の落ち込みが続き、長期間にわたるとうつ病などの精神疾患につながるリスクがあります。
2.過眠症(ナルコレプシー、特発性過眠症)
過眠症は、日中に過剰な眠気が現れる状態です。特に、ナルコレプシーは、急に眠気に襲われるだけでなく、感情が高まったときに筋肉の力が抜けてしまう(カタプレキシー)こともあります。 ナルコレプシーは、脳内の神経伝達物質(オレキシン)の異常が関与しているとされていますが、完全には解明されていません。特発性過眠症は、原因不明で、夜間の睡眠が十分でも昼間の眠気が解消しないのが特徴です。例えば、学生が授業中に急に眠くなり、講義中に何度も眠ってしまうため、単位を落としたり友人関係に支障が出たりするケースも見られます。
過眠症を放置した結果、仕事中や運転中に意識を失うように眠ってしまい、重大な事故につながったケースも少なくありません。
3.睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)
睡眠中に呼吸が一時的に止まる、または極端に弱くなる障害で、いびきをかく人によく見られます。ひどい場合は、1時間に30回以上の無呼吸状態になることもあります。
睡眠時無呼吸症候群は、喉の筋肉が弛緩して気道を塞ぐタイプ(閉塞型)と、脳の呼吸中枢の異常によるタイプ(中枢型)があります。肥満やアルコール摂取、加齢もリスク要因です。パートナーに「いびきがひどい」と言われるが本人は気づかず、日中の強い眠気や頭痛、倦怠感が続くケースが多いです。
放置すると高血圧、心疾患、脳卒中のリスクが高まるだけでなく、日常生活でも集中力低下や認知機能の低下が問題となります。
4.概日リズム睡眠障害
体内時計が正常に機能せず、生活リズムとズレが生じる障害です。「夜眠れない」「朝起きられない」が典型的な症状です。
夜更かしや不規則な生活、夜勤などのシフト勤務が影響します。また、スマホやパソコンのブルーライトも体内時計を狂わせる原因になります。
放置すると長期間の睡眠不足により免疫力が低下し、風邪を引きやすくなるほか、メンタルの不調も引き起こします。
5.むずむず脚症候群(RLS: Restless Legs Syndrome)
寝るときや休息中に脚がむずむずしてじっとしていられなくなり、動かすことでしか不快感を軽減できない状態です。夜間に脚の不快感で何度も目が覚めてしまい、朝は疲れが取れないと訴える患者が多いです。
病気の発症には、鉄欠乏性貧血や腎不全、糖尿病、遺伝的要因が関わっていることがあります。適切な治療を受けないと、慢性的な睡眠不足により、日中の活動が制限され、仕事や家事に支障をきたします。
睡眠障害の診断と検査
- 問診と睡眠日誌の記録:何時に寝て、何時に起きたか、途中で目が覚めた時間などを記録することで、生活リズムや睡眠の質が把握できます。
- ポリソムノグラフィー(PSG):脳波や呼吸、心拍数などを調べる検査で、無呼吸や異常な脳波活動を検出します。
- アクチグラフ検査:腕に小型の装置をつけ、数日間にわたって日常生活での活動量と睡眠リズムを測定します。
睡眠障害の治療法
まずは生活習慣の改善が重要です。就寝時間と起床時間を一定に保ち、寝る前のスマホやカフェインを控えます。
薬物療法
不眠には睡眠薬、むずむず脚症候群には鉄剤など、症状に応じた薬が使われます。
認知行動療法(CBT-I)
寝る前の不安やネガティブ思考を改善し、自然な眠りを促します。
CPAP療法
 無呼吸症候群には、マスクを装着して呼吸をサポートする治療法が有効です。
無呼吸症候群には、マスクを装着して呼吸をサポートする治療法が有効です。
睡眠障害は決して「一晩寝れば治る」ような単純なものではありません。適切な診断と治療を受ければ、ほとんどの場合で改善が期待できます。大切なのは、自分の眠りに問題があると感じたら早めに専門医に相談することです。しっかりとした眠りを取り戻し、心身ともに健康な毎日を送りましょう。