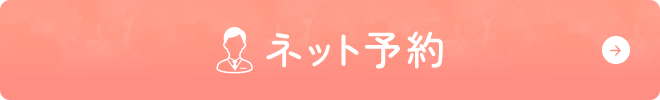パニック障害とは
 パニック障害は、突然理由もなく、強い不安や恐怖に襲われる病気です。発作(パニック発作)は突然起こり、心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、手が震えるなど、身体的な症状が現れます。この発作が数分から30分程度続くことが多く、初めて経験したときには「死んでしまうのではないか」「心臓が止まるのでは」と感じることがあります。
パニック障害は、突然理由もなく、強い不安や恐怖に襲われる病気です。発作(パニック発作)は突然起こり、心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、手が震えるなど、身体的な症状が現れます。この発作が数分から30分程度続くことが多く、初めて経験したときには「死んでしまうのではないか」「心臓が止まるのでは」と感じることがあります。
一度発作を経験すると、「また起こったらどうしよう」と不安になり、その不安が日常生活にも影響を与えるようになります。電車や人混みを避けるようになったり、家から出るのが怖くなったりすることもあります。
しかし、パニック障害は適切な治療を受ければ改善が可能です。発作が治まるだけでなく、予期不安も徐々に軽減され、安心して日常生活を送ることができるようになります。
当院では、土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、日常生活に支障をきたすまえに、お気軽にご相談ください。
パニック障害の症状
パニック障害には、3つの大きな特徴的な症状があります。
パニック発作
突然の身体的な症状が現れ、数分から30分ほどでピークに達します。
- 動悸や胸の痛み:「心臓が激しく動いて止まりそう」「胸が締め付けられる」
- 息苦しさや窒息感:「空気が吸えない」「息が詰まる感じ」
- めまい、ふらつき:「立っていられない」「その場に倒れそう」
- 発汗、冷や汗:「急に汗が出て止まらない」
- 手足のしびれや震え:「力が入らない」「指先がピリピリする」
- 吐き気や腹痛:「胃が重く、吐きそうな感覚」
- 強い死への恐怖感:「このまま死ぬかもしれない」「どうしようもない恐怖」
予期不安
一度発作を経験すると、「また起こるのではないか」と常に不安を抱くようになります。
- 「電車に乗ると発作が起こるかも」
- 「人前で発作が起きたら迷惑をかける」
- 「一人のときに発作が来たら助けてもらえない」
など、この不安が日々の行動に影響し、リラックスできなくなります。
広場恐怖
発作が起こったときに「助けが得られない」と感じる場所(電車、バス、商業施設、エレベーターなど)を避けるようになります。ひどくなると外出そのものが怖くなり、家に引きこもることもあります。
発この広場恐怖については、広場恐怖症という名前でパニック障害とは別の病気として分類されています。症状の特徴や生活への影響に応じて異なる治療が必要です。
パニック障害の原因
パニック障害の原因は一つだけではなく、さまざまな要因が複雑に関係しています。
- 脳内の神経伝達物質の乱れ
脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れると、危険信号を過剰に感じやすくなり、パニック発作が引き起こされます。 - 遺伝的な要因
家族にパニック障害や不安障害があると、発症するリスクが高くなることがわかっています。 - ストレスや環境的要因
・過労、仕事のプレッシャー、家族の問題など、日常のストレスが引き金になることがあります。
・トラウマ体験や事故など、過去の心的ストレスも関係しています。 - 性格的な傾向
心配性、慎重で完璧主義な人は、ストレスに敏感で発症しやすいとされています。
パニック障害の検査・診断
パニック障害の診断には、まず詳しく症状を聞くことから始まります。
- 問診
発作の頻度、起こる場面、症状の詳細を確認します。また、予期不安の程度や日常生活への影響についてもお聞きします。 - 心理テスト
不安障害やうつ病が隠れていないかを評価するため、心理テストが行われることもあります。 - 身体検査
他の病気が原因で発作が起こっている可能性を除外するため、次のような検査が行われることがあります。
・血液検査(甲状腺ホルモンの異常を確認)
・心電図(不整脈がないか確認)
・呼吸機能検査
パニック障害の治療法
 パニック障害の治療には、薬物療法と心理療法の両方が重要です。
パニック障害の治療には、薬物療法と心理療法の両方が重要です。
- 薬物療法
・抗うつ薬(SSRI):セロトニンのバランスを整え、発作を予防する(例:パロキセチン、フルボキサミン)
・抗不安薬:発作が起きたときの即効性がある(例:アルプラゾラム、ロラゼパム)
※依存性があるため、短期間の使用に限定されます。 ・β遮断薬:動悸などの身体的な症状を抑える(例:プロプラノロール) - 認知行動療法(CBT) 不安を引き起こす考え方を修正し、「発作が来ても乗り越えられる」と感じられるよう訓練します。徐々に発作が怖い場所へ行く訓練(エクスポージャー療法)を行い、回避行動を減らします。
- リラクゼーション法 深呼吸や瞑想、ヨガなどを用いて、発作が起きたときでも落ち着けるスキルを身につけます。
パニック障害の予防法
 パニック障害を予防し、再発を防ぐためには、心と体のバランスを整える生活が大切です。
パニック障害を予防し、再発を防ぐためには、心と体のバランスを整える生活が大切です。
- 規則正しい生活
毎日決まった時間に寝て起きることで自律神経を整えます。 - ストレス管理
こまめに休息をとる、適度な運動(ウォーキングや軽いストレッチ)を行い、心身のリフレッシュを心がけましょう。 - バランスの良い食事
精神を安定させる栄養素(マグネシウム、ビタミンB群)を意識して摂ることが大切です。
(例:魚、ナッツ、野菜) - アルコールやカフェインを控える
カフェインは交感神経を刺激し、不安を強めることがあるため、控えるのが望ましいです。 - 無理をせず、相談する
一人で抱え込まず、家族や友人、医師にサポートを求めることで、不安を軽減できます。
パニック障害はつらい症状ですが、適切な治療を受ければ必ず改善します。一歩ずつ自分のペースで進めることが大切です。もし不安を抱えている場合は、早めに医師に相談してくださいね。安心できる生活は必ず取り戻せます。