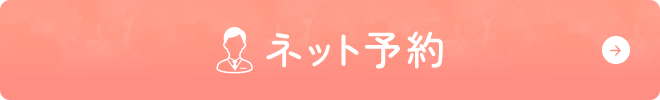発達障害とは
 発達障害とは、脳の働きに違いがあることで、コミュニケーションや行動、学び方に特徴が現れる状態を指します。広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、さまざまな種類があります。それぞれに合った理解と支援がとても大切であり、発達障害は「脳の個性」として受け入れることが望ましいとされています。
発達障害とは、脳の働きに違いがあることで、コミュニケーションや行動、学び方に特徴が現れる状態を指します。広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、さまざまな種類があります。それぞれに合った理解と支援がとても大切であり、発達障害は「脳の個性」として受け入れることが望ましいとされています。
当院では、発達障害の診断が可能です。土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、日常生活に支障をきたすまえに、お気軽にご相談ください。
主な発達障害の分類
- 自閉スペクトラム症(ASD: Autism Spectrum Disorder)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
- 学習障害(LD: Learning Disability)
大人の発達障害
子供の発達障害は、幼少期から小学校の低学年にかけて症状が現れることが多く、親や先生が気づきやすいです。学校での学習や友人との付き合いに課題が現れ、集中力やコミュニケーションに問題が見られます。親や先生からの支援が中心で、学校生活や遊びの中での適応が課題になります。早い段階で適切なサポートを受けると、成長に良い影響を与えます。家庭や学校を中心に、特別支援教育や学習サポートが行われます。
一方で、大人の発達障害は、子供の頃からあった可能性が高いですが、大人になるまで気づかれないことも多いです。特に、仕事や対人関係でのつまずきをきっかけに診断される場合があります。職場での業務や人間関係、日常生活での自己管理に苦労することがあり、ストレスやプレッシャーで症状が悪化することもあります。
心理療法やカウンセリング、職場環境の調整などで生活の質を高めることができます。職場での理解や配慮、カウンセリングやストレス対処法の学習が重要です。適切な支援があると、能力を活かしやすくなります。
発達障害の原因
発達障害は、遺伝的な要因や成長環境などが複雑に影響して脳の働き方が変わると考えられています。親の育て方や本人の努力不足が原因ではありません。
そのため、発達障害を「その人らしい個性」として理解し、受け入れる社会が求められています。早期の診断と適切な支援を受けることで、その人が自信を持って自分らしく生きていくことができます。周囲の温かいサポートがあれば、困難を乗り越え、可能性を大きく広げることができるでしょう。
発達障害の診断
発達障害の診断には、専門医による総合的な評価が欠かせません。診断は、次のようなステップで進められます。
- 問診:本人、保護者、学校の先生などから丁寧に情報を集めます。
- 行動観察:普段の生活でどのような行動が見られるかを観察します。
- 知能検査:知的な発達の度合いを測るテスト(例:WISCなど)を実施します。
- 専門的な評価ツール:発達の特性を詳しく評価するために、ADOS-2などのテストを用います。
早期に診断することがとても大切です。特に、子どもが集団生活に馴染めなかったり、発達の遅れが気になる場合や、大人の方が仕事や人間関係に支障をきたすような場合は、早めに専門機関での診察を受けることをおすすめします。
発達障害の治療
発達障害への支援には、薬物療法だけでなく、教育的や心理的なサポートを組み合わせた総合的なアプローチが効果的です。その人に合った支援プログラムを通して、コミュニケーション能力や対人スキルの向上を目指します。
行動療法(ABA: 応用行動分析)
小さな成功体験を積み重ねながら、良い行動を引き出して強化する手法です。
薬物療法
ADHDなどの場合、集中力を高めるためにメチルフェニデートなどの薬が使われることがあります。
環境の見直し
学校や職場でその人が過ごしやすいように環境を整えることも大切です。静かな場所で作業する、わかりやすい指示を出すなどの配慮が有効です。
カウンセリングと家族支援
子供の場合でも大人の場合でも、周りの方が正しい知識を持つことで、より効果的な支援が可能になります。家族も適切な対応法を学び、安心して支えられる環境を整えることが重要です。 発達障害の支援には、それぞれの人に合った柔軟な対応が求められます。専門家と協力しながら、安心して成長できる環境を一緒に整えていきましょう。
自閉スペクトラム症とは
 自閉スペクトラム症(ASD: Autism Spectrum Disorder)は、生まれつきの脳の発達の特性によって、コミュニケーションの取り方や考え方、感覚の捉え方などが少し異なる状態を指します。一般的な「病気」とは違い、風邪のように治るものではなく、その人の個性や特性の一部として生涯にわたって影響します。
自閉スペクトラム症(ASD: Autism Spectrum Disorder)は、生まれつきの脳の発達の特性によって、コミュニケーションの取り方や考え方、感覚の捉え方などが少し異なる状態を指します。一般的な「病気」とは違い、風邪のように治るものではなく、その人の個性や特性の一部として生涯にわたって影響します。
ASDは「スペクトラム(連続体)」と呼ばれるように、人によって症状の現れ方や強さが大きく異なります。ある人はほとんど困りごとがなく生活できる一方で、ある人は日常生活において大きな支援を必要とすることがあります。そのため、一人ひとりの特性をよく理解し、適切なサポートを考えていくことが大切です。
ASDの主な特徴
ASDの特徴は、大きく分けて以下の3つの領域に現れることが多いです。
1. 対人関係やコミュニケーションの特徴
ASDの方は、対人関係やコミュニケーションの取り方に独自の特徴を持っています。ただし、すべてのASDの方が同じようなコミュニケーションの苦手さを持つわけではなく、人によって違います。
言葉のやりとりに特徴がある
- 相手の気持ちを察したり、空気を読むのが難しい
- 会話の中で、言葉を文字通りに受け取りやすい(例:「手を貸して」と言われたとき、本当に手を出してしまう)
- 冗談や皮肉、比喩表現(「猫の手も借りたいほど忙しい」など)が理解しづらいことがある
- 話すことが得意な人もいるが、一方的に自分の興味のある話を続けてしまうこともある
視線や表情の使い方に特徴がある
- アイコンタクトを取るのが苦手、または長時間見つめることが難しい
- 表情があまり変わらず、感情が伝わりにくいことがある
- 相手の表情を見ても、その感情を正しく読み取るのが難しい
対人関係の築き方に特徴がある
- 一人でいることを好む場合もあるが、必ずしも「友達を作りたくない」というわけではない
- 相手の気持ちを察するのが苦手なため、人間関係で誤解されやすいことがある
- ルールを重視しすぎてしまい、臨機応変な対応が苦手なことがある(例:ゲームのルールを厳密に守ることにこだわりすぎる)
2. こだわりの強さや興味の偏り
ASDの方は、特定の物事へのこだわりが強く、一度興味を持つと深く探求する傾向があります。
ルーチンやルールを重視する
- 日々の生活の中で「いつもと同じ」が安心するため、急な予定変更に対して強いストレスを感じる
- 決まった順番で物事を行わないと落ち着かない(例:通学・通勤ルートを変えると混乱する)
- 手順やルールを細かく決め、それが守られないと不安になる
特定のものへの強い興味
- 特定の分野(例えば鉄道、宇宙、昆虫、歴史など)に非常に詳しくなる
- 同じ映画や本を繰り返し見る、または特定のキャラクターに強くこだわる
- 自分の興味のあることをずっと話し続けることがある
感覚の過敏さまたは鈍感さ
- 音、光、におい、肌触りなどに対して過敏だったり、逆に鈍感だったりする
- 特定の音が苦手で、大きな音(掃除機や花火の音など)に驚きやすい
- 特定の食べ物の食感が苦手で、食事のバリエーションが限られることがある
ASDの強みと困りごと
ASDの強み
ASDの方には、独自の強みがあります。
- 興味のある分野に対して高い集中力を発揮する(研究職、デザイン、プログラミングなどの分野で活躍することが多い)
- ルールや約束をきちんと守る(誠実で正直な人が多い)
- 論理的に物事を考え、パターンやルールを見つけるのが得意(数学やデータ分析、エンジニアリングの分野で強みを発揮することがある)
- 繰り返しの作業や細かい作業が得意(高い精度が求められる仕事で能力を発揮できる)
ASDの困りごと
一方で、社会生活を送る上での困難もあります。
- 対人関係で誤解されやすい(思ったことをそのまま口に出してしまい、相手を傷つけることがある)
- 集団生活のルールに馴染みにくい(学校や職場で暗黙のルールを理解するのが難しいことがある)
- 環境の変化に適応しにくい(新しい場所や状況にストレスを感じやすい)
ASDの方へのサポート方法
ASDの方が自分らしく生活できるようにするためには、周囲の理解と工夫が必要です。
わかりやすい伝え方を工夫する
- あいまいな表現を避け、具体的に伝える(「後でやってね」ではなく、「3時になったらやろうね」など)
- 視覚的なサポートを活用する(予定表やピクトグラムを使うと理解しやすい)
環境を整える
- 急な変更を避け、事前に説明する
- 音や光の刺激が少ない環境を整える
得意なことを活かせる場を見つける
- 興味のある分野での活躍の機会を増やす
- 特性に合った仕事や学習方法を選ぶ
ASDは、人それぞれ特性の現れ方が違う「発達の個性」です。得意なこともあれば、苦手なこともあります。大切なのは、その人の特性を理解し、無理なく過ごせる環境を整えることです。ASDを持つ方が自分らしく生きられるよう、周りの人が理解を深め、支え合うことが何よりも大切です。
注意欠陥・多動性障害とは
 注意欠陥・多動性障害(ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder)は、生まれつき脳の働き方に特性があり、「注意のコントロール」「衝動の抑制」「活動の調整」が難しい状態を指します。これは病気というよりも、脳の特性による発達の個性のひとつであり、環境や支援によってその人の強みを活かすことができます。
注意欠陥・多動性障害(ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder)は、生まれつき脳の働き方に特性があり、「注意のコントロール」「衝動の抑制」「活動の調整」が難しい状態を指します。これは病気というよりも、脳の特性による発達の個性のひとつであり、環境や支援によってその人の強みを活かすことができます。
ADHDの特性は大きく分けて「不注意」「多動性」「衝動性」の3つですが、人によって現れ方が異なります。例えば、不注意の特性が強い人もいれば、多動性や衝動性が目立つ人もいます。また、成長するにつれて特性の表れ方が変化することもあります。
ADHDの主な特徴
ADHDの特徴は、大きく以下の3つに分けられます。
1. 不注意(集中力の持続が難しい)
ADHDの方は、興味のあることには強く集中できる一方で、長時間注意を維持することが難しい傾向があります。
- 話を聞いていても、途中で別のことが気になり、内容を覚えていない
- 授業や会議で集中しようとしても、ふとした刺激(外の音や机の上のもの)に気を取られてしまう
- 興味のあることには過度に集中し、時間を忘れてしまう(ハイパーフォーカスと呼ばれる)
- 書類の記入漏れや計算ミスが多い
- 提出物の締め切りを忘れがち
- 必要なものを持っていくのを忘れる(学校や職場での忘れ物が多い)
- 宿題や仕事をやろうと思っても、なかなか取りかかれない
- 締め切りが迫ってから焦って取り組むことが多い
- タスクの優先順位をつけるのが苦手で、重要でないことに時間をかけてしまう
2. 多動性(じっとしているのが苦手)
ADHDの方は、体を動かしている方が落ち着くことが多く、じっとしていることが難しい場合があります。
- 授業中や会議中に足を揺らしたり、ペンを回したりする
- 長時間座っているのが苦手で、立ち歩いてしまう
- 運転中にじっと座っているのが苦痛に感じる
- 思いついたことをすぐに話してしまう
- 話を聞いている途中で割り込んでしまうことがある
- 話があちこちに飛びやすく、まとまりがなくなることがある
- 図書館や会議室など、静かな場所でじっとしていると落ち着かない
- テレビや音楽がないと集中できない場合がある
- 活動的な環境のほうが力を発揮しやすい
3. 衝動性(考える前に行動してしまう)
ADHDの方は、衝動的に行動してしまうことがあり、トラブルにつながることもあります。
- 会話の途中で相手の話を遮ってしまう
- 考える前に発言してしまい、後で後悔することがある
- 場の空気を読まずに発言してしまい、相手を驚かせることがある
- 財布を持たずに外出してしまう
- 深く考えずに買い物をしてしまい、後で後悔する
- 感情が高ぶると、すぐに行動に移してしまう(怒って物を投げるなど)
- スピードを出しすぎてしまうなど、危険な運転をしてしまうことがある
- ギャンブルやネットショッピングで衝動的にお金を使いすぎることがある
- 衝動的にSNSに投稿し、後で後悔することがある
ADHDの「強み」と「困りごと」
ADHDの強み
ADHDの特性を活かせば、優れた能力を発揮することができます。
- 創造性が豊かで、新しいアイデアを思いつくのが得意
- 興味のあることには集中力を発揮し、専門性を高めることができる
- エネルギッシュで行動力があり、チャレンジ精神が強い
- 直感的に動くのが得意で、危機的状況でもすばやく判断できる
ADHDの困りごと
一方で、環境によっては生活しにくさを感じることもあります。
- 時間の管理が苦手で、遅刻や締め切りを守るのが難しい
- 計画的に物事を進めるのが苦手で、タスク管理に苦労する
- 集中力が続かず、やるべきことを後回しにしてしまう
- 人間関係で衝動的な発言をしてしまい、誤解を招くことがある
ADHDの方へのサポート方法
ADHDの特性を理解し、適切なサポートを行うことで、生活しやすくなります。
環境を整える
- 作業する場所を整理し、気が散るものを減らす
- 静かな環境より、適度に刺激がある場所のほうが集中しやすいこともある
時間管理をサポートする
- スマホのアラームやタイマーを活用する
- oDoリストやスケジュール帳を使って、やるべきことを視覚化する
ルールや仕組みを作る
- 仕事や家事を小さなステップに分け、1つずつ取り組む
- ご褒美を設定することで、モチベーションを維持する
得意なことを活かせる環境を選ぶ
- ルーチンワークよりも、自由度の高い仕事のほうが向いていることが多い
- 自分の特性を理解し、無理のない方法で働くことが大切
ADHDは、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性を持つ発達の個性です。環境や工夫次第で、その人ならではの強みを活かすことができます。大切なのは、本人が困りごとを感じたときに適切な支援を受けられることです。周囲の理解とサポートがあれば、ADHDの方も自分らしく活躍できる社会になります。
学習障害とは
 学習障害(LD: Learning Disability)は、知的な発達には大きな遅れがないにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」などの特定の学習能力に困難が生じる状態を指します。生まれつきの脳の特性によるものであり、本人の努力不足や知的な問題ではありません。
学習障害(LD: Learning Disability)は、知的な発達には大きな遅れがないにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」などの特定の学習能力に困難が生じる状態を指します。生まれつきの脳の特性によるものであり、本人の努力不足や知的な問題ではありません。
LDには様々なタイプがあり、人によって困りごとの現れ方が異なります。そのため、特性を理解し、適切なサポートを行うことで、得意な分野を活かしながら学びやすい環境を作ることが重要です。
LDの主な種類と特徴
LDには大きく3つのタイプがあり、それぞれ困難を感じる分野が異なります。
1. 読字障害(ディスレクシア)
読むことに困難があるタイプ
- 字を正しく認識しにくい
o 文字がバラバラに見えたり、逆さまに見えたりすることがある(例:「b」と「d」、「p」と「q」などを混同する)
o 単語を途中で読み飛ばしたり、順番を間違えてしまうことがある - 読解力に影響が出る
o 文章を読むのに時間がかかるため、授業のスピードについていくのが難しい
o 文字を追うことにエネルギーを使うため、内容を理解する余裕がなくなる - 音読が苦手
o 読み間違いが多く、スムーズに読めない
o 文の途中でつっかえてしまい、読むことに強いストレスを感じる
一方でディスクレシアは、耳で聞いた情報のほうが理解しやすいことが多い、イメージや映像で物事を考えるのが得意な場合があるなどといった特徴もあります。
2. 書字障害(ディスグラフィア)
書くことに困難があるタイプ
- 文字を書くのに時間がかかる
o 頭の中では分かっていても、書くのに時間がかかる
o 文字のバランスが崩れたり、漢字の形がうまく整わなかったりする - 文章を組み立てるのが難しい
o 考えを文章にまとめるのに苦労する
o 句読点の使い方や文の構成が分かりにくくなる - 書くことへのストレス
o 字を書くこと自体が苦手で、メモを取るのを避けることがある
o テストや作文で「書くこと」に時間を取られ、内容が十分に表現できないことがある
一方でディスグラフィアは、口頭で説明すると分かりやすく伝えられることがある、タイピングのほうが書くよりスムーズに思考を整理できることがあるなどといった特徴もあります。
3. 算数障害(ディスカリキュリア)
数や計算に困難があるタイプ
- 数字の概念がつかみにくい
o 「数がどれくらいの大きさか」の感覚が分かりにくい(例:「100」は「10」の10倍であることが直感的に理解しにくい)
o 時計の読み方やお金の計算が苦手 - 計算が苦手
o 繰り上がりや繰り下がりを理解するのが難しい
o 暗算が苦手で、筆算をしても間違えやすい - 数式の理解が難しい
o 文章問題の意味を読み取るのが難しく、どの計算をすればいいか分からない
o 九九を覚えるのに時間がかかる
一方でディスカリキュリアは、数の概念ではなく図やイメージで物事を考えるのが得意なことも多く、数字よりも言葉や映像を使って考えると理解しやすい場合があります。
LDの「強み」と「困りごと」
LDの強み
LDの方は、特定の分野で苦手を感じる一方で、他の分野では優れた能力を発揮することが多いです。
- 言葉や数字よりも、図や映像で物事を理解するのが得意
- 想像力が豊かで、独自のアイデアを生み出す力がある
- 意な分野に集中すると、専門的な知識を深めやすい
- 口頭での説明や実演での学習のほうが力を発揮しやすい
LDの困りごと
一方で、学校や職場では困難を感じやすい場面もあります。
- 授業のスピードについていけず、学習意欲を失いやすい
- 書く・読む・計算することに時間がかかり、苦手意識を持ちやすい
- 努力不足」や「怠けている」と誤解されやすい
- 自信を失い、学習や仕事に対するモチベーションが下がってしまうことがある
LDの方へのサポート方法
LDの特性を理解し、適切な支援を行うことで、より学びやすい環境を作ることができます。
学習方法を工夫する
- ディスレクシアの方には、音声教材や読み上げ機能を活用する
- ディスグラフィアの方には、タイピングや音声入力を推奨する
- ディスカリキュリアの方には、具体物を使った学習(ブロックや図など)を取り入れる
環境を整える
- 必要に応じて時間延長や課題の提出方法を柔軟にする
- 試験や評価の方法を工夫し、苦手な分野が過度な負担にならないようにする
得意な分野を活かす
- 読むのが苦手なら、聞いて学ぶ方法を取り入れる
- 書くのが苦手なら、話して伝える手段を活用する
- 計算が苦手なら、計算機やアプリを活用する
学習障害(LD)は、「読む」「書く」「計算する」といった特定の分野に困難がある発達の特性です。しかし、それは決して知的な問題ではなく、学び方の違いに過ぎません。適切なサポートを受ければ、得意なことを活かして活躍することができます。
大切なのは、本人が「できない」と感じることを減らし、「自分に合った学び方」を見つけることです。周囲の理解と支援があれば、LDの方も自分らしく成長し、活躍することができます。