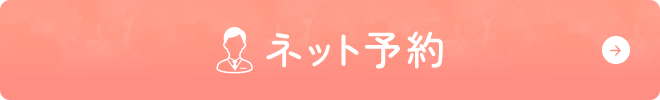認知症とは
 認知症は、記憶力や判断力、考える力が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。単なる加齢による物忘れとは異なり、症状は進行し、元に戻ることはありません。代表的な種類として、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症があります。それぞれ原因や症状が異なり、治療法やケアの方法も違います。
認知症は、記憶力や判断力、考える力が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。単なる加齢による物忘れとは異なり、症状は進行し、元に戻ることはありません。代表的な種類として、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症があります。それぞれ原因や症状が異なり、治療法やケアの方法も違います。
当院では、土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、「何かいつもと様子が違うな」と気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
認知症は、精神科と脳神経内科のどちらを受診する?
認知症の診察は、脳神経内科でも精神科でも受けられますが、どちらを選ぶかは症状によって変わります。 脳神経内科は、アルツハイマー型認知症や血管性認知症など、脳そのものに関わる病気を診る専門の科です。記憶力の低下や認知機能の変化が気になる場合に、詳しく検査し原因を探るのに適しています。脳の状態を調べるための画像検査や神経学的な診察が行われ、病気の進行具合に応じた治療が行われます。
一方で、精神科は気持ちの落ち込みや不安感、幻覚や妄想といった精神的な症状が強い場合にサポートができます。認知症になると、物忘れだけでなく気分の変化や行動面での問題が現れることがありますが、そうした心のケアを中心にサポートしてくれるのが精神科です。
もし、「記憶や思考の問題がメイン」なら脳神経内科に相談するのが良いでしょう。「気分が沈んでいる」「幻覚が見える」といった精神的な症状が強いと感じるなら、精神科の受診が勧められます。また、症状によっては脳神経内科と精神科が連携しながら治療を進めることもあります。どちらに行けば良いか迷ったときは、まずは一度当院へご相談ください。専門医の力を借りて、一人で抱え込まず早めの受診を心がけましょう。
認知症の症状
認知症は、初期・中期・末期と進行するに従って、症状が段階的に変化します。
初期の症状
- 物忘れ:最近の出来事を思い出せない。何度も同じ質問をする。
- 時間や場所が分からなくなる:今が何時なのか、どこにいるのか分からなくなる。
- 判断力の低下:買い物や料理など、日常の複雑な作業が難しくなる。
中期の症状
- 行動や性格の変化:怒りっぽくなる、急に不安を感じる。
- 幻覚や妄想:家族を疑う、見えないものが見える。
- 生活能力の低下:身の回りのことができなくなり、支援が必要になる。
末期の症状
- コミュニケーションの困難:言葉が少なくなる、意思表示が難しくなる。
- 身体機能の低下:食事や排泄などで完全な介助が必要になる。
- これらの症状により、本人だけでなく、家族や介護者の負担も大きくなります。
認知症の原因
認知症は脳の神経細胞が減少することで発症し、その原因は種類によって異なります。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は最も一般的なタイプで、脳にアミロイドβやタウといった異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が次第に破壊されていく病気です。遺伝的要因もあり、特に家族性早発性アルツハイマー病は遺伝子変異が関係しています。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血などの血管障害が直接の原因で発症します。急に症状が現れることが特徴であり、高血圧や糖尿病といった血管疾患がリスクを高めます。適切な血圧管理が予防に重要です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症はレビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質が脳内に蓄積することで起こります。幻視や注意力低下、パーキンソン症状が典型的な症状です。慢性的なストレスや外傷がリスク要因とされることもあります。
前頭側頭型認知症
前頭葉および側頭葉が萎縮することで発症し、初期には行動や感情の変化が目立ちます。社会的行動の変化、判断力の低下が特徴で、若年性認知症の一部として知られています。
その他の原因
慢性的なアルコール依存症、ビタミン欠乏、低血糖、感染症(例:クロイツフェルト・ヤコブ病)なども認知症の原因となることがあります。栄養状態の改善や適切な治療が早期介入のカギです。
このように、認知症にはさまざまなタイプが存在し、それぞれ異なる原因とリスクが関与しています。症状や進行度によって治療方針が異なるため、早期診断が重要です。
認知症の診断方法
認知症は、問診や検査を通じて診断されます。
- 問診
本人や家族から、症状がいつから始まったか、どのように進行しているかを詳しく聞き取ります。 - 認知機能検査
ミニメンタルステート検査(MMSE)やモントリオール認知症評価(MoCA)を使い、記憶や注意力を測定します。 - 画像検査
MRIやCTで脳の萎縮や血管障害を確認します。レビー小体型認知症の場合、脳の特定部位の変化が見られることもあります。 - 血液検査
他の病気(栄養不足や甲状腺機能低下など)が原因ではないかを確認します。 - 詳細な神経心理検査
記憶力や言語能力などをより詳しく評価し、認知症の種類を特定します。
認知症の治療とケア
認知症は現在のところ完治することは難しいですが、進行を遅らせたり、症状を緩和させたりする治療ができます。
薬物療法
アルツハイマー型認知症には、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)やNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が使われます。
ア精神症状(不安、幻覚、妄想)には抗精神病薬や抗不安薬を用いることがあります。
生活環境の工夫
部屋の中にラベルを貼るなど、日常生活で迷わないよう工夫します。また、毎日決まった時間に決まった行動をすることで安心感を与えます。
非薬物療法
- 認知リハビリテーション:簡単な計算や会話、趣味活動で脳を活性化します。
- 運動療法:軽い体操や散歩で血流を良くし、気分転換を図ります。
このように、認知症は早期発見と適切な治療が重要です。患者さんと家族が安心して生活を続けられるよう、医療機関や地域の支援を活用しましょう。
認知症予防に役立つ生活習慣
 認知症を完全に防ぐことは難しいですが、日々の生活で次のような工夫をすることでリスクを下げる効果が期待できます。
認知症を完全に防ぐことは難しいですが、日々の生活で次のような工夫をすることでリスクを下げる効果が期待できます。
- 脳を使う活動を取り入れる
読書やパズル、趣味、ゲームなど、頭を使う活動は脳の活性化に役立ちます。新しいことに挑戦するのも効果的です。 - 適度な運動を習慣化する
ウォーキングやヨガ、軽いジョギングなどの有酸素運動は、脳への血流を促進し、健康維持に繋がります。 - バランスの良い食事を心がける
魚や野菜、オリーブオイルを豊富に使った地中海式の食事は、脳に良いとされ、特に抗酸化作用のある食品が推奨されています。 - 積極的な社会的交流を行う
友人や家族との会話、地域のイベントやサークル活動に参加することで孤立を防ぎ、心の健康にもプラスになります。 - 生活習慣病を適切に管理する
高血圧や糖尿病、肥満の予防と治療をしっかり行うことで、脳の血管障害を減らし、認知症リスクの低減に繋がります。
毎日の小さな積み重ねが、認知機能の維持に大きく寄与するため、意識的に取り組むことが大切です。