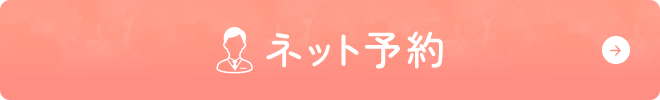自律神経失調症
 自律神経失調症は、体を動かす時に働く「交感神経」と、休む時に働く「副交感神経」のバランスが乱れた時に、心や体にさまざまな不調が現れる病気です。このバランスが崩れると、疲れやすくなったり、体の調子が悪いと感じたりします。見た目にはわかりにくいため、「なんとなく具合が悪い」という症状が特徴です。
自律神経失調症は、体を動かす時に働く「交感神経」と、休む時に働く「副交感神経」のバランスが乱れた時に、心や体にさまざまな不調が現れる病気です。このバランスが崩れると、疲れやすくなったり、体の調子が悪いと感じたりします。見た目にはわかりにくいため、「なんとなく具合が悪い」という症状が特徴です。
当院では、土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、日常生活に支障をきたすまえに、お気軽にご相談ください。
自律神経失調症の症状
自律神経失調症では、体の不調と心の不調があらわれます。
体の不調
- 慢性的なだるさ:朝起きても疲れが取れず、体が重く感じます。
- めまい・ふらつき:立ち上がるとクラッとすることがよくあります。
- 頭痛:特にストレスがたまった時や緊張した後にズキズキと痛むことがあります。
- 動悸:突然、心臓がドキドキしたりバクバクしたりします。運動していなくても起こるのが特徴です。
- 冷えやのぼせ:手足が異常に冷えたり、逆に顔だけがほてることがあります。
- 胃の不調:ストレスを感じた時に胃がムカムカしたり、食べたものが重く感じることがあります。
- 便秘や下痢:急にお腹が痛くなり下痢をすることがある一方で、便秘が続くこともあります。これらが交互に起こる場合は、過敏性腸症候群と関連することが多いです。
心の不調
- イライラや不安感:小さなことでイライラしたり、漠然とした不安が消えないことがあります。
- 抑うつ感:何をするにもやる気が起きず、気分が沈みやすくなります。
- 睡眠障害:寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、早朝に目が覚めてその後眠れないといった症状がよく見られます。
自律神経が乱れる原因
① ストレスの影響
仕事や家庭、人間関係などで感じるストレスは、交感神経を優位にし続けてしまいます。交感神経は本来、「緊張状態」や「危険を回避する時」に働くものですが、これが長引くと副交感神経が十分に働けず、体が常に戦闘モードのような状態になってしまいます。その結果、疲れがたまり、眠れないなどの悪循環が起こります。
② 不規則な生活の影響
夜更かし、長時間のスマホ・パソコン使用、食事を抜いたりするなど、不規則な生活は、体内時計が乱れる原因となります。体内時計が崩れると、自律神経のリズムも乱れやすくなり、朝に体がだるい、日中に眠い、夜に眠れないといった症状が出てきます。
③ 季節の変わり目や天気
春や秋の季節の変わり目、梅雨時期、台風などの気圧の変化は、体に思った以上のストレスを与えます。特に自律神経が敏感な人は、気圧の低下によって頭痛やだるさを感じやすくなります。
④ ホルモンバランスの変化
女性の場合、月経周期によってホルモンバランスが変動しやすいため、それに伴って自律神経が乱れやすくなります。また、更年期にはホルモンの分泌が大きく変わるため、症状が強く出ることがあります。
自律神経失調症の治療とセルフケアのポイント
① 規則正しい生活
- 朝のリズムを整える:朝起きたらまず日光を浴びることで、体内時計がリセットされます。これが睡眠のリズムを改善し、夜もスムーズに眠れるようになります。
- 同じ時間に寝る習慣をつける:たとえ短時間でも質の良い睡眠を目指しましょう。寝る前のスマホやパソコンの使用は控え、ぬるめのお風呂に入るのも効果的です。
② 軽い運動を取り入れる
- ウォーキング:無理のないペースで20~30分程度歩くと、体がリラックスし、副交感神経が活発になります。
- ストレッチ:朝や寝る前に軽いストレッチをするだけでも、緊張がほぐれ、心身のバランスが整いやすくなります。
③ ストレスマネジメント
- マインドフルネス:今この瞬間に集中する練習です。深い呼吸に意識を向けたり、ゆっくりとした動作でストレッチを行ったりすると、心が落ち着きます。
- 認知行動療法:ネガティブな考え方をポジティブに捉える方法です。カウンセラーのもとで行うことも効果的ですが、自分で日記を書く習慣も役立ちます。
④ 食事の見直し
- 腸内環境を整える食材:発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌)や食物繊維が豊富な野菜を取り入れましょう。腸は「第2の脳」と呼ばれるほど自律神経に影響を与える重要な臓器です。
- ビタミンやミネラルを摂取する:ビタミンB群やマグネシウムは神経を落ち着かせる効果があります。豚肉やナッツ類、バナナがおすすめです。
⑤ 専門的な治療が必要な場合
- 自律神経調整薬:漢方薬やビタミン剤を使って自律神経のバランスを整えることがあります。
- 抗不安薬や抗うつ薬:ストレスや不安が原因で症状が強い場合に処方されることがありますが、医師の指導のもとで服用するのが重要です。
無理にすべてを変える必要はありません。まずは、毎日の生活でできそうなことから取り組みましょう。「朝に日光を浴びる」「少し散歩をする」「寝る前のスマホをやめてみる」といった、小さな工夫が大きな変化につながります。
大切なのは、自分の体や心に「今日もよく頑張っているね」と声をかけるような、優しい気持ちで向き合うことです。焦らずに、少しずつ心と体のバランスを取り戻していきましょう。
過敏性腸症候群
 過敏性腸症候群(IBS)は、腸に明確な病変がないにもかかわらず、腹痛や便通異常(下痢や便秘)が慢性的に続く病気です。腸の過敏な反応や、ストレス・自律神経の乱れが主な原因とされ、現代社会では多くの人が悩んでいます。特にストレスや心理的要因が症状を悪化させることが多く、心と体の両面からの治療が必要です。
過敏性腸症候群(IBS)は、腸に明確な病変がないにもかかわらず、腹痛や便通異常(下痢や便秘)が慢性的に続く病気です。腸の過敏な反応や、ストレス・自律神経の乱れが主な原因とされ、現代社会では多くの人が悩んでいます。特にストレスや心理的要因が症状を悪化させることが多く、心と体の両面からの治療が必要です。
IBSの症状が慢性的に続いたり、日常生活に支障をきたしたりする場合には、精神科や心療内科を受診することで、薬物療法や心理的サポートによる改善が期待できます。体だけでなく、心の状態も含めて適切なケアを受けることが大切です。
当院では、土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、日常生活に支障をきたすまえに、お気軽にご相談ください。
過敏性腸症候群(IBS)の症状
過敏性腸症候群(IBS)の症状は、主に腹痛やお腹の不快感、そして便通異常が中心です。腹痛は食事の後やストレスを感じた時に強まることが多く、排便をすると痛みが和らぐのが特徴です。
便通の異常としては、下痢が頻繁に起こる下痢型、硬い便が出にくくなる便秘型、そして下痢と便秘を交互に繰り返す混合型があり、人によってパターンが異なります。また、腸内にガスが溜まることでお腹が張った感じが強くなり、腹部膨満感を訴えることもよくあります。さらに、トイレに行った後も便が残っているような感覚(残便感)が続き、何度もトイレに行きたくなることもあります。
これらの症状は、ストレスや不安が原因で悪化することが多く、日常生活に影響を与えることがあります。
過敏性腸症候群の原因
過敏性腸症候群(IBS)の原因は、まだ完全には明らかではありませんが、以下の要因が関与していると考えられています。
- 脳と腸の連携の乱れ:脳と腸は深くつながっていて、ストレスや不安が腸に影響を与えると、腸が敏感に反応してしまいます。
- 自律神経のバランスの崩れ:ストレスが原因で自律神経が乱れると、腸の動きが正常に働かなくなり、下痢や便秘が起こりやすくなります。
- 腸が敏感になっている状態:ちょっとした刺激でも腸が過剰に反応し、腹痛や下痢が出やすくなります。
- 腸内環境の乱れ:腸内の良い菌と悪い菌のバランスが崩れると、腸の調子が悪くなり、便通が不安定になります。
過敏性腸症候群の診断方法
過敏性腸症候群の診断は、他の病気を除外しつつ、症状をもとに判断します。主に以下の方法が用いられます。
- 問診(症状の詳細な聞き取り)
便通のパターンや腹痛の頻度、ストレスとの関連などを確認します。 - ローマⅣ基準に基づく診断
腹痛が3か月以上続き、排便と関連する症状があるかどうかを評価します。 - 除外診断のための検査
• 血液検査:炎症や貧血の有無を確認。
• 便検査:感染性腸炎や便潜血の確認。
• 大腸内視鏡検査:腸内のポリープや炎症の有無を調べる。 - 腸内環境の評価(必要に応じて)
腸内細菌検査や水素呼気試験で腸内環境の異常を確認します。
過敏性腸症候群の治療方法
1. 食事療法
腸で発酵しやすい食品(小麦、乳製品、豆類など)を制限することで、ガスや腹痛を軽減します。(低FODMAP食)また、便秘には不溶性食物繊維(野菜や玄米)、下痢には水溶性食物繊維(オートミールやこんにゃく)が効果的です。腸の働きをスムーズにするため、水を十分に摂取するようにしましょう。どの食べ物で症状が出るかを記録し、自分に合わないものを把握することも大切です。
2. ストレス管理
リラクゼーション法(ヨガ、瞑想、深呼吸など)で心身の緊張を和らげ、副交感神経を優位にします。認知行動療法で、ストレスに対する考え方や反応を見直し、心の負担を軽減します。 趣味や好きなことに時間を使い、ストレスを軽減しましょう。リラックスできる時間を意識的に確保することも重要です。
3. 運動療法
軽い有酸素運動(ウォーキングやストレッチ)は腸の動きを改善し、ガスの排出にも役立ちます。
4. 薬物療法
- 腸の動きを整える薬:腸の過剰な活動を抑える薬や、動きを促進する薬が使用されます。
- 抗不安薬・抗うつ薬:脳腸相関の乱れを改善し、ストレスが原因の症状を緩和します。
- プロバイオティクス:腸内環境を整えるため、乳酸菌やビフィズス菌を含むサプリメントが役立つことがあります。
過敏性腸症候群は、ストレスや腸の過敏な反応が関与するため、生活習慣の見直しと精神的なケアが重要です。症状が慢性的であっても、適切な治療と日常生活の改善によってコントロールが可能です。医師と相談しながら、自分に合った治療方法を見つけていきましょう。